
今回は、「見えないところにこそ価値がある」ものづくりの真髄を体感できる場所タカラスタンダード川越ショールームを訪問してきました。住宅設備における放浪素材のトップランナー、タカラスタンダード。その魅力と技術をじっくりとご紹介します!

目次
1. タカラスタンダードってどんな会社?
創業はなんと明治45年(1912年)。最初はホーロー鍋から始まり、今ではキッチンやバスルームなど住宅設備に特化したメーカーへと成長。2025年で113周年を迎える、まさに“職人魂”の塊のような企業です。
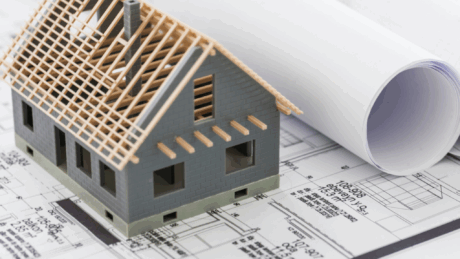
2. ホーローという素材へのこだわり
タカラスタンダードといえば「高品位ホーロー」。ガラス質の美しさと金属の強さを兼ね備えたこの素材は、キズや汚れに強く、長持ちするのが魅力。しかも最近では、インクジェット技術によって、まるで木目や石目のようなリアルなデザインも表現可能に!
3. 川越ショールームの魅力とは?
展示の見せ方がとにかく“体感型”。ただ見るだけでなく、実際に浴槽に入ったり、扉や天板を組み合わせてカラーコーディネートを試せたりと、住まい手の目線で考えられた工夫が詰まっています。
4. キッチン展示の特徴
価格帯ごとにシリーズが並んでおり、比較検討がしやすいのがポイント。中でも注目は、10年間ファン掃除不要のAI搭載レンジフード。見た目も性能も妥協しない、タカラの本気が詰まっています。
5. お風呂の構造が丸見え!体験型展示
断熱材の配置やフレーム構造まで、「見えないところ」をあえて見せる展示スタイルに感動!震度6強に耐える安心構造は、まさに命を守る技術。安全性をしっかり実演で伝えてくれるのが素晴らしいです。
6. 耐震性能と安全への配慮
フレームの剛性が高く、他社のボルト脚と比べて圧倒的に安定。入浴中の地震リスクにも備えられる、安心設計が徹底されています。

7. 洗面化粧台の工夫と収納力
サイズや収納棚のアレンジも自由度が高く、放浪素材でいつまでもキレイ。水まわりの衛生性と使いやすさを両立した、毎日の暮らしに寄り添う設計です。
8. ホーローと最新技術の融合「インクジェット柄」
ホーロー=地味という時代はもう終わり。艶を消したマットホーローや、本物の木のような質感の扉など、驚くほど洗練されたデザインが登場しています。これぞ技術革新!
9. スタッフの案内が素晴らしい理由
案内してくださった杉山さんをはじめ、スタッフの皆さんの知識と親身さが印象的でした。「ものづくりの誇り」が会話ににじみ出ているんです。
10. ショールーム訪問のすすめ
カタログでは伝わらない“質感”や“使用感”は、ぜひ実際にショールームで体感してください。斎藤も強くオススメします!

タカラスタンダード川越ショールームを訪れて感じたのは、「本物のものづくりとは、見えない部分にこそ魂を込めることだ」ということです。目に見える美しさや高機能だけでなく、日常では意識しづらい安全性や清掃性、そして永く使える耐久性すべてにおいて妥協のない設計がなされていました。
特に感動したのは、ホーローという素材への一貫したこだわりです。一見硬そうで加工が難しい印象のある放浪を、ここまで柔軟に、美しく、使いやすく昇華させているのは、まさにタカラスタンダードならではの技術力と情熱の賜物。
ショールームも非常に分かりやすく、無駄な動線がなく、訪れるお客様の立場に立った配置や説明が行き届いています。「このメーカーは安心してお客様に勧められる」と、改めて感じさせられる訪問となりました。
住まいの設備を選ぶ際、「長く快適に使いたい」という想いがあるなら、タカラスタンダードは必ず検討してほしいメーカーの一つです。ぜひ一度、ショールームに足を運んでみてください。
【お知らせ】
このような住宅の最新情報や、省エネ住宅の実例などを発信しています。
ぜひYouTubeチャンネル登録をして、快適な住まいづくりにお役立てください。
また、齊藤建設は、高性能で省エネな家づくりをしています。
埼玉県鶴ヶ島市を中心に、南は朝霞市、北は深谷市まで広く活動していますので、
省エネ住宅に関するご相談がございましたらお気軽に株式会社齊藤建設までお問い合わせください!
それでは、また次回のコラムでお会いしましょう!
