「2025年問題」というと、介護や医療の話に思われがちかもしれませんが、実は私たち建設業界にも大きな影響を与えるテーマなのです。
団塊の世代の引退が本格化し、職人の高齢化と若手不足が深刻化している今。
現場では、「人がいない」「進まない」「教える人がいない」といった声が当たり前のように聞こえてくるようになりました。
でも、この問題は決して「業界のピンチ」だけではありません。見方を変えれば、「業界のチャンス」でもあると私は思っています。
なぜなら、建築という仕事は、人の暮らしを支える「生きる力」に満ちた職業だからです。しっかりと学び、経験を積めば、一生続けられる誇りある仕事。
今こそ、建設業の本当の魅力を再発見し、次の世代につなげていくタイミングではないでしょうか。
このコラムでは、現場で感じているリアルな課題とともに、業界全体がどう変わっていくべきか、そして若い人たちにとってどんな可能性があるのかを、
現場の声と、未来への希望を込めて——どうぞ最後までお付き合いください。
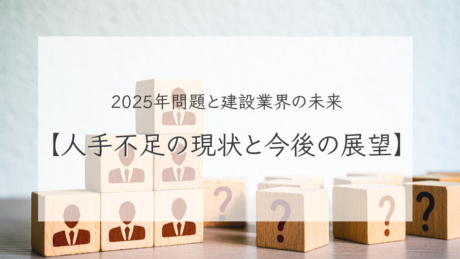
目次
1. 2025年問題とは?
「2025年問題」とは、団塊の世代(1947年〜1949年生まれ)が75歳以上の「後期高齢者」となることで、医療・介護・年金など、社会保障制度への負担が一気に増大するという日本全体の構造的な課題を指します。2025年には、日本の人口の5人に1人が後期高齢者になると予測されています。
この問題は、少子高齢化が加速する中で、日本のあらゆる産業に人手不足や生産性低下といった影響を及ぼします。医療・介護だけでなく、運輸業や製造業、そして我々のいる建設業界もまた、直接的にその影響を受ける分野なのです。
つまり2025年問題は、高齢者向けサービスの問題だけではなく、若者世代の雇用、教育、税負担、そしてインフラ維持など、日本社会全体の「仕組み」を見直さなければならない、大きな転換期を意味しています。

2. 建設業界における影響
建設業界にとって、2025年問題は非常に現実的で深刻な課題です。
現場で働く職人や技術者の高齢化が急速に進んでおり、とくに大工や左官、設備業など手作業が中心の職種では、団塊の世代に頼っているケースが多く、彼らの引退によって、現場に大きな穴が空くことが予想されます。
例えば、現在の建設業従事者のうち、およそ3割が60歳以上と言われており、大工職に至っては65歳以上が6割を占めるとも。
これはつまり、10年以内にその大半が引退するということ。しかも、若年層の新規参入が圧倒的に少ないため、次世代へのスムーズなバトンタッチができていないのです。
また、現場では「ベテランがいなくなったら、誰が教えるのか?」という問題も生まれています。
職人技術は長年の経験と現場感覚に基づくものであり、単に教科書で学べるものではありません。だからこそ、技術の継承が進まないまま退職者が増えていく現状は、建設業界全体の持続性を脅かしているのです。
さらに、これらの人手不足の影響は、施主側にも現れてきています。
新築工事やリフォーム工事の着工が大幅に遅れ、数ヶ月〜数年待ちになるケースが珍しくなくなってきました。
「建てたいのに、人がいないから建てられない」という現象が、今すでにリアルに起き始めているのです。
3. 職人の高齢化と人手不足の現状
現在の建設業界では、65歳以上の職人が多数現役で活躍しています。しかし、体力や視力の衰えにより、かつてのような精密な作業が難しくなってきているのも事実です。
特に注文住宅やリフォームなど、丁寧な手仕事が求められる現場では、高齢職人の存在が施工品質の維持に欠かせない状況です。それだけに、引退や体調不良による離職が現場に大きな影響を及ぼしています。
一方で、若手の数が圧倒的に少なく、技能継承の時間的猶予も少ないため、結果的に「1人の職人が背負う仕事量」が年々増加。1人あたりの年間着工棟数も増加傾向にあり、負担の偏りがますます問題視されています。
4. 若者が建設業界に入らない理由
建設業界が「若者離れ」している最大の理由は、いまだに根強く残る「3K(きつい・汚い・危険)」のイメージ。さらに、親方からの厳しい指導、見て覚えろ文化、そして福利厚生の未整備が、若者たちを遠ざける要因となっています。
他業種と比べても、建設業の初任給はやや高めであり、やりがいもある職種です。しかし、SNSや動画で様々な働き方を知っている今の若者にとって、「安定性」や「成長環境」がなければ魅力を感じてもらえません。
働きたいと思える「環境づくり」こそが、これからの業界の最大の課題とも言えます。
5. 長時間労働と社会保険の問題
建設業は、他業界と比べて労働時間が長いというイメージが強く、事実、繁忙期には長時間労働となる現場もあります。また、「一人親方」や「常用大工」といった立場では、社会保険や労災保険に加入していないケースも多く、法の隙間で働いている実態があります。
本来、社員のように働いている人には、最低限の保障と休暇が必要です。しかし、会社側にその体制が整っていない、あるいは整える余裕がないことも多く、若者が安心して入ってこれない構造になってしまっています。
このようなグレーゾーンを改善し、誰もが正当な権利のもとで働けるような業界にしていく必要があります。
6. 技術継承の難しさ
建設業の技術は「現場での経験」によって培われます。図面や教科書では学びきれないノウハウがあり、それをいかに次世代へ伝えるかが業界全体の大きな課題です。
しかし、いまだに「見て覚えろ」の精神が根強く、実際に手を動かす機会をなかなか与えられない若者が多く存在します。さらに、教える側の職人にも「教え方がわからない」という悩みがあり、結果として技術が伝わらないままベテランが引退していくという悪循環が生まれています。
この問題を解決するには、現場任せにせず、会社として教育制度や研修体制を整える必要があります。

7. 建設業界の倒産・廃業問題
ここ数年、建設業界では「黒字廃業」が急増しています。つまり、仕事はあるし利益も出ているのに、後継者がいないために事業を畳まざるを得ないケースです。
特に中小の工務店では、創業者世代が高齢化し、子や社員に事業を引き継ぐことが難しいという実情があります。こうした廃業は、統計には「倒産」として出ないため見えづらいものの、業界全体に大きな穴を開けています。
結果として、リフォームや新築を希望しても「職人がいない」「工務店がない」という状況が地域に発生しており、今後ますます深刻化すると見られています。

8. 未来の職人にとってのチャンス
一方で、この人手不足の状況は、若者にとっての大きなチャンスでもあります。今から技術を学び、経験を積めば、数年後には第一線で活躍できる職人になれる可能性が大いにあるのです。
需要が高まる一方で供給が追いつかない中、技術のある職人は“引く手あまた”。将来的には独立して工務店を立ち上げる道も見えてきます。
建設業は、やりがいがあり、人の生活を支える誇りある仕事。将来性を見据えて挑戦したい若者にとって、まさに「狙い目の職業」なのです。

9. 業界の改革とデジタル活用
近年、建設業界でも「デジタル化」「働き方改革」の波が押し寄せています。施工管理をクラウドで行う現場、オンラインで研修を行う制度、3D図面やAR/VRを使ったプレゼンテーションなど、今や建設業も“アナログ”一辺倒ではなくなってきています。
また、スマートフォンやタブレットでの現場報告、デジタルツールによる工程管理などによって、若者にとっても親しみやすい環境が整いつつあります。
「古い業界」と思われがちな建設業ですが、今こそ変革の真っ只中。ここに飛び込んでくる若者には、まさに“先駆者”として活躍できる舞台が広がっています。
10. まとめ:未来の建設業を支えるために
2025年問題は、建設業界にとって避けられない現実です。しかし、それを「危機」と捉えるだけではなく、「再構築のチャンス」として前向きに捉えることもできます。
私たちが今できることは、まず第一に、若い世代が安心して働ける環境づくりを進めること。そして次に、技術の伝承を企業の責任としてしっかり仕組みにすること。さらに、建設業の魅力を、もっと多くの人に伝えていくことです。
家づくりは、人の暮らしを支える仕事です。その中で働く人の人生をも豊かにする力があります。今、若者にとって建設業は「しんどそう」ではなく、「やりがいがあって夢のある仕事」であることを、私たちが示していかなくてはなりません。
未来を担う若い力とともに、この業界をもっと良い方向へ育てていきたい。そんな想いを持って、私たち斎藤建設も取り組みを続けています。
建設業に希望を感じる皆さん、ぜひ一歩を踏み出してみてください。そして、同じ業界で奮闘する仲間たちともに、明日の建設業界を一緒に作っていきましょう。
【お知らせ】
このような住宅の最新情報や、省エネ住宅の実例などを発信しています。
ぜひYouTubeチャンネル登録をして、快適な住まいづくりにお役立てください。
また、齊藤建設は、高性能で省エネな家づくりをしています。
埼玉県鶴ヶ島市を中心に、南は朝霞市、北は深谷市まで広く活動していますので、
省エネ住宅に関するご相談がございましたらお気軽に株式会社齊藤建設までお問い合わせください!
それでは、また次回のコラムでお会いしましょう!
